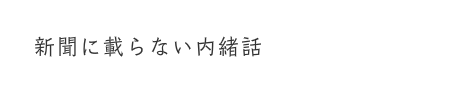新聞に載らない内緒話 Vol.05
64歳になったら
私事ながら、5月は誕生月である。63歳になる。定年延長もあと2年、さてどうしたものだろう。 ポール・マッカートニーに「When I'm Sixty-Four(64歳になったら)」という名曲がある。1967年に発表されたアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」に収録されている。「年をとって 僕の髪の毛がなくなっても、僕のこと頼りにしてくれますか?」「僕が64歳になっても、食事を作ってくれますか?」そんな歌詞が続く。もっとも、老年を憂う歌ではない。恋人に向け、「64歳になっても僕を愛してくれるかい」というプロポーズ、つまりラブソングである。10代のころに作ったようで、父親の64歳の誕生日をきっかけに再び日の目を見ることになった、と聞く。うらやましい。当方にはとっくに無縁、である。先日、中学時代の同級生と一杯、やる機会があった。ひとしきり旧交を温め、いざお開きの段になると各自、カバンをまさぐり、手にした紙袋から錠剤を取り出す。「そりゃ何だ?」「高血圧…降圧剤だよ」というわけで、テーブル上はカプセル、錠剤のオンパレード。「これが効く」「こっちはサッパリだ」と盛りあがった。この年になれば、病とは無縁ではない。そう言えば当方も近年、原因不明の尋常性疥癬(かいせん)で病院通いである。右足は変形性膝関節症。パソコンに向かって年中、記事を書き続けているからか目はショボショボ、左肩は慢性の張りに悩まされている。先日は左足親指の、「巻き爪」で手術まで受けた。「治療法はいろいろありますが、手術が一番。でも少々、痛いですよ」爪を点検しながら、医師は念を押した。そうはいっても歩くたびに痛むし、何かに擦っただけで飛び上がるほどである。麻酔注射を3本も打たれ、必死に耐えて15分ほどの手術は終わった。「よく悲鳴を上げませんでしたね。泣きわめく人がいるくらいですからね」と、年配の医師は含み笑いで褒めてくれたから、言ってやった。「こっちだって、徒(いたずら)に年を取っている訳じゃないよ。世間体がある」63歳の貫禄、というものである。どうでもよいけど。余談ながら、ポール・マッカートニーは2006年6月18日に64歳の誕生日を迎えたが、皮肉にもその直前に再婚相手のヘザー・ミルズとの離婚を発表したと、Wikipediaにはある。 ★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで。
新聞に載らない内緒話 Vol.04
野球賭博と、「思うにまかせぬこと」
1993年(平5)4月20日、東京会館で「丸谷才一さんと『女ざかり』の会」が催された。『女ざかり』は、政府・与党から圧力がかかった大新聞の女性記者論説委員・南弓子が友人身内を動員、窮地を脱する新聞社小説(新聞小説ではない)で、この日のパーティーはその出版絡みであったろう。席上、著者の丸谷才一さんがあいさつに立つのだが、その折の裏話?が著書「挨拶はたいへんだ」(朝日新聞社発行)に記されている。要約すると、丸谷さんがある時、毎日新聞社社長に会った折「(毎日に)女の論説委員ってゐませんね」と問いかけると、その1か月後女性論説委員が誕生したという。さらに数か月後、朝日新聞社にも女性論説委員が生まれた。その数年後、読売文学賞のパーティーで、社長(当時)の渡辺恒雄さんが寄ってきて、こう言ったそうだ。以下は原文を掲載する(ちなみに丸谷さんの文章は全て旧仮名遣いである)。「一つ教へていただきたいことがあるんだが・・・」「はい、どうぞ」「あの女の論説委員、モデルは誰です?」「ゐませんよ。まったくのフィクション」「さうですか。いろいろ考へたがどうにもわからなかった」「読売に女の論説委員はゐませんね」「作らうと思ってね。一人いいのがゐたんですが、勉強させようと思ってワシントン支局へやったのがまづかった。アメリカの男と恋愛して、退社してしまった」丸谷さんはこの文章をこう締めくくっている。「世には、ナベツネさんでも思ふにまかせぬことがある」◆さて、清原問題に続いて、またも巨人絡みの不祥事が発覚した。巨人は3月8日、東京都内で記者会見を開き、新たに同球団の高木京介投手(26)が野球賭博を行っていたことを明らかにし、謹慎処分を科したと発表。渡辺恒雄最高顧問、白石興二郎オーナー、桃井恒和会長が揃って、引責辞任することになった。球団社長は「多くの方に迷惑をかけたことや(読売の)調査が及ばなかったことに責任を感じている」と謝罪した。飼い犬に手を噛まれる、とはまさにこのことで、球団挙げての刷新を誓った矢先の発覚である。さぞかしあの剛腕・渡辺恒雄最高顧問も再発防止へ御腐心されたとは思うが、さしずめ「丸谷流」に言えば、「世には、ナベツネさんでも思うにまかせぬことがある」ということか。心中お察し申し上げる。(2016年4月)
新聞に載らない内緒話 Vol.03
桜、北上
「花の雲鐘は上野か浅草か」 江戸深川で、芭蕉が詠んだ句である。雲と見まがうばかりの、桜の盛りが「花の雪」に織り込んである。のほほんとした空に、鐘の音がゆったりと漂ってゆく。
例年、東京の桜は3月末あたりが満開である。桜の名所は数々あれど、作家の池波正太郎さんが愛したのは、上野寛永寺・両大師堂の境内にある「御車返しの桜」だった。この桜は、一本の木に一重と八重の淡い紅色の花が同時に咲く。
ここの桜は咲くのが遅い。上野恩賜公園や不忍池周辺の桜がひとしきり咲き乱れ、葉桜になった頃、池波さんは保温ボトルに熱かんを詰め訪れた。陽が傾き、カラスがねぐらに帰るころ、静まりかえった境内でひとり桜を眺め、酒をふくむ。絶景であると、何かのエッセイに書かれていたと思う。東京の桜が散った頃、東北本線(在来線)に乗って北上してみたらよい。落花1週間後ほどが見ごろと思うが、例えば「宇都宮を過ぎるあたりから散り残った花びらが現れ、白河、郡山と進むにつれてビデオを逆回転させたように桜の美しさがよみがえり、大河原―船岡間の白石川堤までくると満開になった。白石川は車窓の花見としては最高だと思う」と書いたのは、鉄道作家・宮脇俊三さんだった。
同氏が編集委員を務めた「鉄道歳時記」(小学館刊)に見える記述である。
「時期を見計らって東北新幹線の上り列車に乗ってみるのもおもしろいだろう」。桜の蕾(つぼみ)から散るまでの花の生涯が「わずか1時間ぐらいで」車窓から楽しめる。梅が「春のめざめ」なら、桜は「爛漫(らんまん)」であろう。日本という国の「長さ」を感じるのもこの季節である。
1月、避寒桜の沖縄地方から、津軽海峡を桜が超えるのはゴールデンウィークであり、北海道の桜は五月(さつき)なのだ。
いずれサラリーマン生活に終止符を打ったら、長い長い桜の旅に寄りそってみたい。
散る桜残る桜も散る桜―。 桜とは、咲く前からすでに思い出のような花である。
新聞に載らない内緒話 Vol.02
忘れかけていた日
娘の誕生日が近づいた。「娘」といっても20歳代半ばも過ぎ、はたしてその形容がふさわしいのかどうか。大学には入ったが、つまらぬと言って中退。海外での2年間は半分勉強、残り半分は放浪?を経て帰国。家を出、独立したから取りあえず一人前、のはずである。今年の、私の誕生日にポロシャツを買ってくれたから、なにか負い目で、返礼をせねばなるまい。さて何がふさわしいのか、何を欲しがるのか、これがサッパリ思い当たらない。
こんな時の親の心境を、作家・青木玉(幸田露伴の孫。幸田文の一人娘であることはご存知と思うが)はこう書いている。
「自分の子育てが終わると、親はおもちゃの流行を忘れ、何歳の子は何に興味を持つかてんで見当が悪くなる。以前、自信を持って子供の欲しいものをぴたりと選んだ時があったなあと郷愁に似た思いで眺めていた」(「上り坂下り坂」講談社刊)
なるほど、そういうことかと合点がいった。とはいえ、誕生日は日増しに近づいてくる。さて、去年は何を贈ったか、記憶をたどったが思い出せない。思い余ってメールを送ってみた。
「誕生日、何か欲しいものはないか?」ホテル勤務の、夜勤明けの「娘」からは「今、起きたところ。ボンヤリしてるので、後にして」と素っ気ない。いくら待っても返信はない。親が「何歳の子は何に興味を持つか、てんで見当が悪くなる」ように、子供も「いつまでも誕生日でもあるまい」というのが本音であろう。恋人、良人(りょうじん)からの申し出ならば目を輝かせるのかも知れないが。
数日後、忘れた頃にメールが届いた。「みんなで食事でもしよう。久しぶりだね」そういうことか。
誕生日とは、物のやりとりの日ではなく、忘れかけていた家族をもう一度、自覚する日なのかも知れない。年を取ると、子に教えられることが多くなる。世の習いとはいえ、ちょいと口惜しい。
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで。
新聞に載らない内緒話 Vol.01
「夏秋」と「春秋」
10月初旬、とあるパーティに招かれた。帰り際、お土産を頂戴した。筒状のそれに、もしやと思い自宅で包みを解いたらやはりカレンダーであった。
ずいぶん気の早い、とページをめくりながら苦笑いした。
そう言えばと、暦を手繰ったらもう11月、お酉(とり)さまの季節である。足立区・花畑、淺草は鷲(おおとり)、新宿の花園など各地で酉の市が立つ。今年は11月 5日(木)一の酉、11月17日(火)二の酉、11月29日(日)三の酉と、三の酉まである。熊手が飾り立てられ、祝儀の手締めが雑沓に響く。
いつの間にか年の瀬は近づいているのである。
やはり同月13日に、山梨を日帰りした。紅葉狩りが目的であった。私がプロ野球担当時代、取材に当たった某球団の、球団代表を務めた方からのお招きで、1日を楽しんだ。すでに都会での生活に見切りを付け、自宅を売却してこの地で自適な生活を営んでおられる。
お住まいは北杜市長坂町の「夏秋(なつあき)」。その地名に惹かれたのも事実である。人生の「春秋」を乗り越え、終の棲家が「夏秋」であろうか。
酒が入り、遠い昔の取材談義に花が咲き、風光明媚(めいび)にひとしきり遊んだ。
◆
十有三(じゅうゆうさん)春秋
逝く者已(すで)に水の如し
天地に始終無く、人生に生死有り。
安(いづく)んぞ古人に類するを得て、
千載(せんざい)青史(せいし)に列せん。
◆
江戸時代の文人・頼山陽、13歳の時の詩である。
その意は、生まれて「春秋」はや13年、水の流れと同様、時の流れは元へは戻らぬ。天地には始めも終わりもないが、人間は生まれたら必ず死ぬ、と解す。
末尾の「青史に列せん」、つまり「昔の偉人のように、千年後の歴史に名をつらねたいものだ」とは私にとって無縁だが、その野望や栴檀(せんだん)の例え、やはり大器であったか。
改めて、手許のカレンダーを繰ってみる。
私にそれは無機質な、単なる数字の羅列でしかないが、その理科的風景に唯ぼんやりと、明日を感じたのは、先取りされたカレンダーのせいであろうか。
★スポーツ、芸能情報は日刊スポーツで。ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル 0120-81-4356まで。